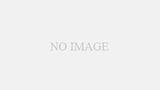最近は日経平均株価が最高値を更新するなど株式市場が話題となることが多いですね。
それでは株価はなぜ変動するのでしょうか?日経平均株価やTOPIXなどの株価指数は日々変動しています。株価の変動要因を知り、経済の流れを抑え、今後の経済予測ができるようにしましょう。
株式の需要と供給
そもそも株式とは株式会社が発行する有価証券です。会社の立ち上げや運営にはまとまった資金が必要になります。そこで会社オーナーの権利を分割して有価証券としてして投資家に購入してもらうことでこの資金を確保します。この発行する有価証券が株式です。
株式は証券取引所に上場されている銘柄もあれば、未上場の株式もあります。ちなみに2022年3月末時点で上場している企業の数は約3,800社になります。投資家はこの株式を売買して株式投資を行っています。
株価が変動する理由
株価が変動する理由は簡単にいえば需要と供給があるからです。会社が発行する株式には限りがあります。そのため限られた株式に対して買いたい人が多ければ株価は上がり、株式を売りたい人が多ければ株価は下がります。
日常でも人気のある商品は高くなり、人気がない商品は安くなるので当たり前のことですね。
そのため株価は需給関係によって上下します。ただしこの需給関係も様々な要因が絡んで起こります。
株価変動の要因
株価の変動には内部要因と外部要因があります。株を発行する企業自体から起こる要因が内部要因、市場など外部から影響を受けるのが外部要因です。
内部要因には企業の業績や設備投資、配当金、新商品などがあります。
外部要因には景気や為替、自然災害、政治などが挙げられます。
株価が変動には内部要因・外部要因がともに重要です。株を売買していく上でこれらに着目して分析を行いましょう。
株価変動の要素
株価変動の要素はいくつかあります。それぞれ株価にどのような影響を与えるのでしょうか。
株価変動の要素をいくつか紹介します。
1.企業業績
株価を決める大きな要因となるのが企業実績です。
企業業績が良ければ株を買いたい人が増えて株価が上がり、反対に業績が悪ければ株を売りたい人が増えて株価が下がる場合が多いです。
そのため四半期ごと業績発表や決算発表後は株価が変動しやすいタイミングです。また業績予想の修正が行われると株価に影響を与えます。そのため企業業績が上方修正される、または下方修正されるなどの情報はこまめにチェックしましょう。
企業業績は日経新聞や会社四季報、各企業のHPなどで確認することができます。
2.配当金
株価の変動要因の2つ目は配当金です。
配当金の増額である「増配」や配当金を復活させる「復配」などが発表されると株価は上がる傾向にあります。配当金目的で買う人が増えるからです。
逆に「減配」などが発表されると株価が下がる傾向にあります。
なお増配や減配などで株価に影響があるかを考えるには配当金額をみるだけではなく、配当利回りや配当性向も確認するようにしましょう。
他企業の同指標と比較することで、検討している株式の配当金額の水準が高いのか低いのを判断する材料となります。
3.新商品の開発
株価の変動要因の3つ目は新商品の開発です。
例えば企業から新商品の開発や発売が発表されると、その期待から株を買いたい人が増え株価が上がる傾向があります。新商品は企業業績に影響を与えるからです。
しかし新商品が投資家の期待よりも低く、売上が見込めない時は株価が上がらないこともあります。
新商品は出すタイミングや市場ニーズに合っているかなど多角的な影響を受け、投資家ごとに売れるか売れないかの判断も異なるため予測しづらい部分もあります。
4.自社株買い
株価の変動要因の4つ目は自社株買いです。
自社株買いとは企業が市場から自社の株式を買い戻すことをいいます。企業は株価の上昇や株主への利益還元を目的として自社株買いを行います。
自社株買いを行うと株価が上がる理由はいくつかありますが、主な理由はROE(自己資本利益利率)の向上とPER(株価収益率)の低下が挙げられます。
ROE(自己資本利益利率)とは企業がどれだけ効率的に資本を使って利益をあげているかを測る指標です。ROEの計算式はROE(%)=当期純利益 ÷ 自己資本 × 100で求められます。ROEが高ければ高いほど、株主資本を効率的に使って利益を獲得しているを示します。そのためROEが高い方が投資家からの期待や評価が高くなります。
そこで自己資本で自社株買いを行うと分母の自己資本(株主資本)が下がるため、ROEは上がります。そうすることで投資家の期待が高まり株価に上昇傾向を与えます。
またPER(株価収益率)は株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのかを判断するために用いられる指標です。PERが低いほど株価は割安で短期間で回収可能性があるのに対して、PERが高い場合は投資コスト回収が長期化して割高とみなされます。
PERは、PER(%)=株価÷EPS(1株当たり純利益)で求められます。そのため自社株買いをして発行株式数が少なくなると、EPSが上がってPERが必然的に下がるため投資家から割安な株として需要が高まり、株価上昇に影響を及ぼします。
5.景気や金利、為替の変動
動株価の変動要因の5つ目は景気や金利、為替の変動です。
現在、日本は長いデフレを抜けてインフレ基調の中にいます。仮に、今後、景気が良くなるとすると企業の業績が良くなり株価上昇が見込まれます。また、金利が上がると企業は借入金の利息支払いが増えるため企業業績が悪くなり株価が下がることがあります。
また為替が変動した場合は業種によって影響が異なります。通常、輸入企業は仕入れ価格が安い方が良いため円高の方が有利であり、逆に輸出企業は高く売れたほうが良いため円安の方が有利になります。
円安によって伸びる業界は自動車、精密機械、電機メーカー、鉄鋼、海運などが挙げられます。
また円高によって伸びる業界は陸運、不動産、倉庫、電力、食品などが挙げられます。
日本の代表的な指数である日経平均株価指数はトヨタやソニー、三菱商事、HONDAなど輸出型企業が主導となって構成されています。そのため円安に進行すると日経平均にとってプラス要因となり株価が上がることが期待されます。逆に円高になると輸出型企業にとってはマイナス要因となるため日経平均も悪影響を及ぼす可能性があります。
6.海外株式市場の影響
株価の変動要因の6つ目は海外株式市場の影響です。
日本の株式市場は海外株式市場の影響を受けており、特にアメリカの影響を大きく受けます。日本の株式市場はアメリカの株式市場の値動きとよく似た動きをすることがあるため、事前にアメリカの株式市場の動きをチェックしておく必要があります。
日本の株式市場には多くの外国人投資家が参入しており、アメリカの株式市場が下落して損失が出ると外国人投資家は損失をカバーするために株を売る可能性があります。そのため日本株式は売りが攻勢となり株価が下がることが考えられます。
逆にアメリカの株式市場の株価が上がれば日本の株式市場も上がる可能性があります。2024年2月にアメリカ半導体大手エヌビディアが2024年1月期の決算が市場予想を上回る好成績だったことを発表し、アメリカのハイテク株が大幅に上昇しました。これを受けて日本の半導体銘柄などのハイテク株が上昇して日経平均株価も大幅上昇し、史上最高値を更新しました。
このように日本の株式市場と海外の株式市場は連動しており、株取引をするにあたってその影響を注視しなければなりません。
7.災害の発生や天候、社会情勢の変化
株価の変動要因の7つ目は災害の発生や天候、社会情勢の変化です。
例えば災害によって企業の工場が被災した場合、業績悪化を懸念して株が売られ株価が下がる場合があります。最近だとイーロン・マスク氏が率いるテスラのドイツ工場が送電塔の放火で停電の影響を受け生産停止の被害に遭い株価が下落しました。
また株価は冷夏や猛暑などの異常気象にも影響を受けます。冷夏で農作物が不作となって価格が上昇したり、猛暑で清涼飲料水が売れて売上が上がるなどがあります。
さらに国内外の政治動向も株価に影響を与えます。戦争や政治的発言などがあったタイミングで株価が動くこともあります。2024年はアメリカで大統領選挙があり、バイデン現大統領とトランプ前大統領の再戦となりますが、どちらが大統領になるかで株価に大きな影響がありそうです。
このように災害や天候、社会情勢は企業業績に左右するため影響が出る場合があります。
株取引を行う前に情報収集
以上のように株価変動にはいろいろな要素が影響します。そのためテレビで見たとか友人が買っているからなどの理由で闇雲に株取引をするのではなく、一歩踏み込んでなぜ株価が上がるのかを考えるようにしましょう。
株取引を行う前に株価が上下する理由を考えることができれば、自身にとって最適な買い時・売り時がわかるようになります。そのためある企業の株式に関心を持ったらできるだけ内的要因、外的要因を調べて考察し、自分で納得した上で取引するようにしましょう。
仮に失敗したとしても、それを繰り返すことによってより理解度が増していきます。自分にとって最適な方法を見つけるため「なぜそれを買うのか?」を考える癖を付け、自分にとって最適なスタイルを見つけましょう。